2050年カーボンニュートラルへの挑戦!世界と日本の取り組み 【後編】
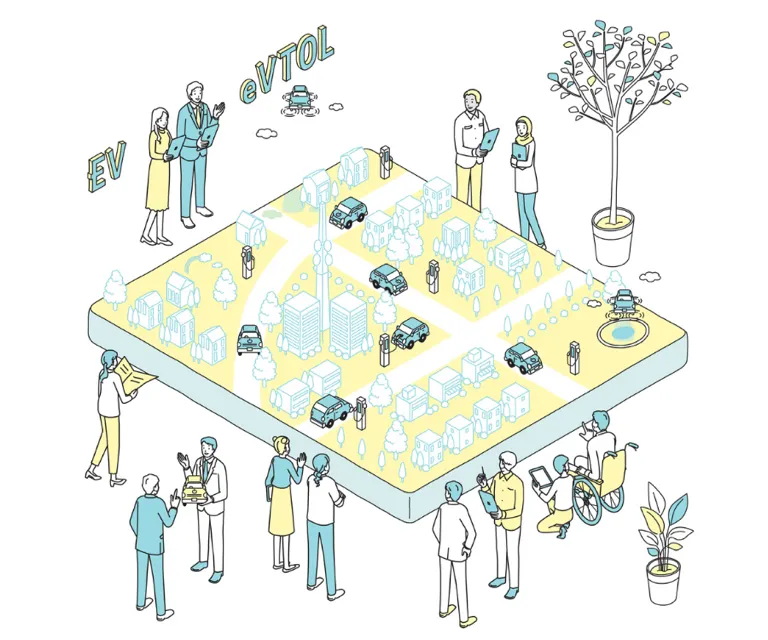
前編では、脱炭素社会の重要性と世界の動向について解説しました。
関連記事:2050年カーボンニュートラルへの挑戦!世界と日本の取り組み【前編】
後編では日本の取り組みと制度が、企業や私たちの暮らしにどのような影響をもたらすのかを、より具体的に掘り下げていきます。
日本の取り組み(2025年現在)
2023年のCOP28で、日本は2013年度比で約20%の温室効果ガス削減を達成したと報告し、一定の進展を示しました。
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、さまざまな政策と実践が進められています。
法整備と支援体制
2024年には「地球温暖化対策推進法」が改正され、地方自治体の適応策や中小企業支援の枠組みが強化されました。
さらには経済産業省と環境省が連携し、GX(グリーントランスフォーメーション)への円滑な移行を支援しています。
日本の主な政策
- GX経済移行債:政府が今後10年間で20兆円の政府資金を投じ、企業や自治体が「脱炭素」に取り組みやすくする仕組み。およそ150兆円以上の投資が動くと期待されています。
- 再生可能エネルギーの導入加速:海の上に風車を建てる「洋上風力発電」や、水素・アンモニアを使った新しい発電方法を拡大。そのためとなる日本中の送電線を整備。
- カーボンプライシング制度:CO₂を出す量に応じて、排出にコストを課す制度を段階的に導入。
- 脱炭素先行地域支援:市や町などの自治体と地元の企業が協力して、再生可能エネルギーを地元で使う仕組みをつくるなど、地域単位でCO₂を減らすプロジェクトを進めています。
地域・自治体での先進事例
地域ごとの特性を活かした温室効果ガス削減を目指し、環境省は「脱炭素先行地域」としてのモデル地域を募集し、2030年までの成果を目標としています。
この取り組みは、全国的な脱炭素化を連鎖的に進める「実行の脱炭素ドミノ」戦略の一環でもあります。
脱炭素先行地域
- 北海道下川町:省エネルギー推進、再生可能エネルギー活用、エシカル消費、自然環境保全、地域資源活用の取り組みを通じて、CO₂の削減を目指しています。
- 長野県飯田市:地域マイクログリッドの構築、太陽光発電設備や蓄電設備の導入など、再生可能エネルギーの活用を積極的に展開。
排出量取引制度(ETS)の導入と期待される効果
2025年から本格導入される「排出量取引制度(ETS)」は、企業ごとにCO₂排出の上限(キャップ)を設定し、それを超えた場合は排出枠を市場で購入し、不足を補う制度です。
逆に、排出量が上限を下回れば余剰分を売却することも可能で、市場原理を活かして温室効果ガスの削減を効率的に進める仕組みとなっています。
企業にとってのリスクとチャンス
ETSへの対応は、企業にとって単なる規制対応にとどまらず、新たなビジネス機会や競争力強化のチャンスにもなります。一方新しい試みのためリスクも大きいでしょう。
チャンス
- 環境対応=企業価値の向上として、ESG投資やSDGs対応に敏感な投資家・顧客からの評価が向上。
- 再生可能エネルギー、エネルギーマネジメント、カーボンオフセット関連の新規事業の創出。
- 排出枠を売却することで収益化も可能。
リスク
- 排出枠の購入費用や、取引先からの取引制限リスクによるコスト増。
- 中小企業を中心とした対応力の格差。
- ETS価格変動リスクや制度運用の複雑さ。
進む企業の取り組みと広がる私たちへの影響
脱炭素社会の実現に向け、国の政策に加えて民間企業も独自の取り組みを進めています。
日本企業の取り組み事例
TOYOTA
- 電動車だけでなく、エンジン搭載車両でのCO2排出量削減にも取り組み、フレックス燃料車(バイオ燃料とガソリンの混合)を導入。
- エンジン搭載車両のCO2削減、CN(カーボンニュートラル)燃料の普及に貢献するエンジンの開発を検討。
- EUの目標に合わせ、2035年新車CO2排出量100%削減を目指す。
Panasonic
- 2050年までに、全世界CO2総排出量の約1%に当たる3億トン以上の削減インパクトの創出。
- 2030年までに全事業会社におけるCO2排出量実質ゼロを目指す。
私たちの生活への影響
こうした動きは企業だけでなく、私たちの暮らしにも少なからぬ影響を与えています。
- 再エネの導入や排出コストの影響で、電気料金の上昇が続く可能性がある。
- サプライチェーン全体でのコスト増により、消費者価格への波及も予想される。
一見すると負担に感じるかもしれませんが、これらの変化は「快適で持続可能な社会」へ向けた未来への投資と捉えることができます。
まとめ
排出量取引制度をはじめとする脱炭素政策は、企業や生活者に行動の変化を求めるものです。しかしそれは、同時に新たな価値創造と持続可能性への挑戦でもあります。
この「変化の時代」を前向きにとらえ、持続可能な社会を築いていくためには、私たち一人ひとりがより良い選択を重ねていくことが、未来の世代に豊かな社会を引き継ぐ第一歩となるでしょう。


